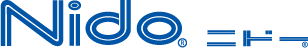ハイテクを駆使する人工毛植毛法

仕上がり感、自然感では群を抜く植毛法が、わが国では欧米ほどポピュラーではないのは、外科的な施術を要するというイメージが先行しているからではないだろうか。
自毛植毛法の場合、それはもっともなのであるが、人工毛植毛法はそのイメージで大いに損していると思う。
なぜなら人工毛植毛法の施術は自毛植毛法のそれとはまったく異質のものであり、本格的な手術を必要としない。包帯もせずに、翌日に仕事へ復帰できるほど、施術の身体的負担は軽い。施術の時間帯によってはその日に職場へ戻ることもできる。
なぜ、そんなことが可能なのか?
その秘密は0.3ミリという極細の針を搭載した植毛装置にある。
優秀な工業デザイナーであった人工毛植毛の開発者は、「α」型毛根の開発と平行して、それを植える植毛装置の研究も熱心に行った。
いい人工毛ができても、植毛装置がおそまつであると元も子もないからである。開発者はここでもその才能をいかんなく発揮した。
人の頭髪は、頭皮のどの部分から生えてきて、その深さは表面からどれくらいかご存知だろうか?
頭皮は上から順に、表皮・真皮・皮下組織とあり、その下も頭蓋骨をか被っている帽状腱膜がある。頭髪は皮下組織にある毛母から生えてくるのだが、その深さはだいたい表皮から2~3ミリである。頭皮全体の厚さは、頭の部位によって違いがあり、4~9ミリといったところだ。個人差も若干ある。
人工毛を植毛する場合、当然ではあるが、いい加減な深さで植えてはダメである。植える深さがまちまちだと、定着率が1本1本バラバラになる。それでは困る。
そうならないためには、常に一定の深さで安全に植える必要がある。
しかし、植えるためのベストの深さは、人によって、そして頭の部位によって違うことは前述した通りである。そこが開発者のアタマを悩ませた。
個人差と部位による違いを乗り越えて、常に一定の深さで植えるにはどうすればよいか。
開発者が試作に継ぐ試作を重ねてたどり着いたのが、自動的に深度を測る測定機のついたディスポーザブル(使い捨て)植毛装置である。
頭皮のすぐ下には頭蓋骨を被っている帽状腱膜があると書いた。この膜は表皮からアプローチする場合、頭蓋骨を被っている最後の膜で、ここを傷つければ甚大な健康障害が生じかねない。
そこで開発者は植毛装置の先端がここに到達すると、それ以上は針が進まない構造にした。その構造はノック式のシャープペンシルに似てなくもない。アタマをノックすれば、先端に人工毛をつけた針は頭皮に刺さり進入していく。そして帽状腱膜に到達したらピタリと止まる。
ここが人工毛を植えるベストの深さなのである。
自動深度装置は特許であるから、どのようなメカニズムを持ってそれが可能となるのか、詳細を明かすことはできないが、この植毛装置の開発によって、きわめて安全に植毛することができるようになった。同時に定着率も向上し、安定してきたのである。
この植毛装置には、もうひとつ繊細な技術が導入されている。
それは極細の植毛針である。
無菌パックから取り出した人工毛は、この針の先端につけて植えるのであるが、刺入する際、人体への負担をできるだけ減じなければならない。
人体への負担を最小限にする鍵は、針の径にある。径が太ければ太いほど、針を差し入れるとき、頭皮に開く孔が太くなり、組織の破壊度が大きくなる。そこで苦心に苦心を重ね、針の径を細くした。その太さが0.3ミリなのである。
0.3ミリがいったいどれくらいの細さか、数字だけではわかりにくいと思う。
注射針を引き合いに出すと、予防接種などを行う際に用いる注射針は、通常、0.4ミリである。
人工毛植毛で使用する植毛針は、世界一細いインスリン注射針に匹敵する細さだ。正確には0.1ミリ太いのだが、使用する場所が違う。
インスリンの自己注射は腕や腹、大腿部など、やわらかい皮下に刺すのであるが、人工毛植毛は硬い頭皮に刺す。
この事実を考えれば、0.3ミリのすごさがおわかりいただけるだろう。これ以上、細くすれば、毛を植えるとき、針が折れ曲がって使えなくなるのである。
この針をもってしても、植毛の際には若干の出血をともなうことがある。それでも皮膚の組織の破壊は最小限に抑えられているので、傷の回復は早い。だからほとんどの場合、施術の翌日に、普段通り仕事場に行くことができるのである。
【ニドーの植毛施術法が気になったら下記テキストをクリック☆】
「ニドーが選ばられる理由は、ニドーの高い技術力にあるよ☆」
参考書籍
「床屋も間違える驚異の毛髪術」 著者:黒木 要